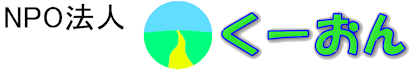更新情報・お知らせ
- 2024/03/31
- 「スケジュール」を更新。
- 2024/01/12
- 「くーおんニュース 第20号」を追加。NEW
- 2023/07/17
- 「2023年 夏休み特別プログラム」を追加。
- 2023/07/07
- 「スタッフの紹介」ページ更新。
- 2023/05/28
- 「くーおんニュース 第19号」を追加。
- 2023/05/28
- 情 報・資 料ページへ「令和5年度 通常総会資料」を追加。
- 2023/04/04
- 「スケジュール」を更新。
- 2022/07/27
- 「2022年 夏休み特別プログラム」を追加。
- 2022/07/14
- 「くーおんニュース 第18号」を追加。
- 2022/05/31
- 「令和4年度 年間行事」を追加。
- 2022/05/29
- 情 報・資 料ページへ「令和4年度 通常総会資料」を追加。
- 2022/04/10
- 「スケジュール」を更新。
- 2021/11/12
- 「第2回 座談会」を追加。
- 2021/11/17
- 「くーおんニュース 臨時号」を追加。
- 2021/10/15
- 「スタッフの紹介」ページ更新。
- 2021/10/15
- 全面リニューアル。
- 2014/08/01
- リニューアル。
- 2012/07/03
- ホームページ開設。
新型コロナウイルス(COVID(コビット)-19)感染症に関するお知らせ
当法人の新型コロナウィルスに対する対応について
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行されました。
今後、当法人の活動における対応の詳細につきましては、こちら (PDF342KB)をクリックしてください。
(PDF342KB)をクリックしてください。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
最新情報
「くーおんニュース」第20号 完成
「くーおんニュース 第20号」が完成しました。
御覧になられる方は、こちら (PDF1,229KB)をクリックしてください。
(PDF1,229KB)をクリックしてください。
前号までの「くーおんニュース」をご覧になられる方は「くーおんニュース」ページをアクセスして下さい。
第2回 座談会
11月16日(木)に〈第2回 座談会〉が開催されました。
当日の様子をまとめた議事録は、こちら (PDF255KB)をクリックしてください。
(PDF255KB)をクリックしてください。
内容をまとめた集計は、こちら (PDF376KB)をクリックしてください。
(PDF376KB)をクリックしてください。
〈意見交換会〉事前アンケート集計
9月16日の〈意見交換会〉を行うにあたり、各事業所を利用する保護者の皆様へ事前アンケートをさせていただきました。。
アンケートの集計は、こちら (PDF224KB)をクリックしてください。
(PDF224KB)をクリックしてください。
「くーおん体操クラブ」新規・体験・見学のお知らせ
「くーおん体操クラブ」新規ご利用のための説明、体験を随時受け付けます。
くーおん体操クラブ スケジュールカレンダー
 =幼児
=幼児  =小学生
=小学生  =中学・高校生
=中学・高校生  =その他
=その他